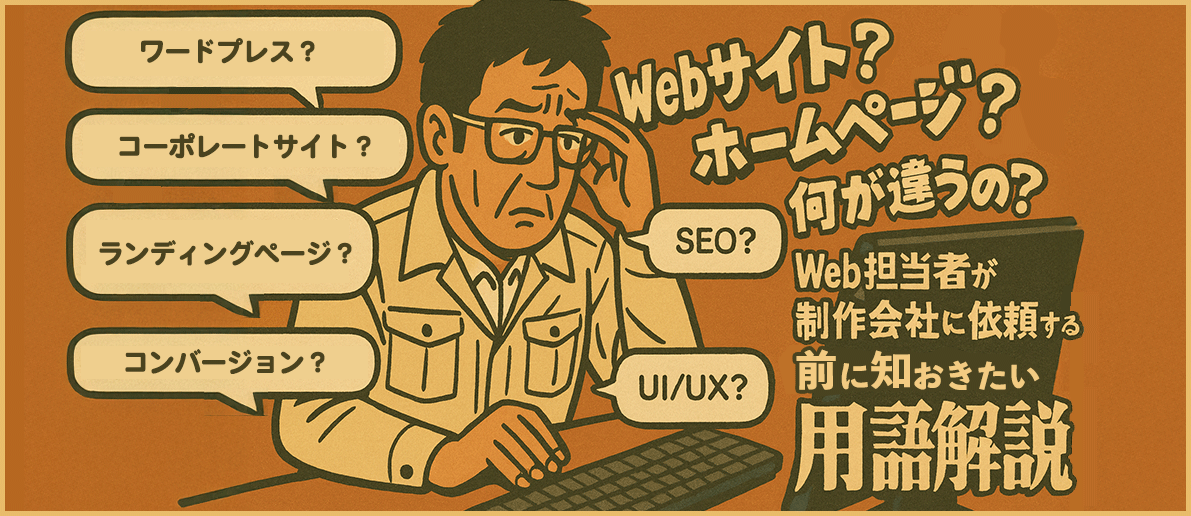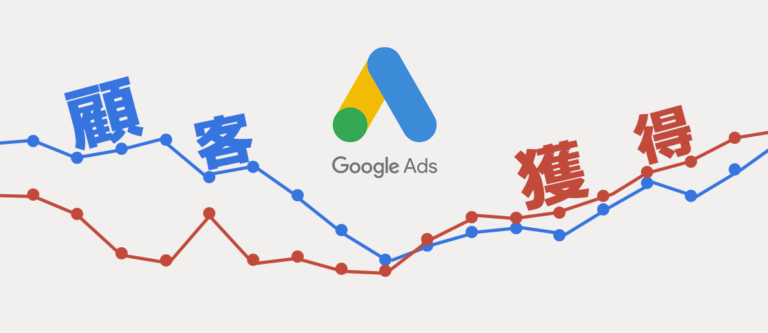「Webサイトとホームページってどう違うの?」そんな疑問を持ったことはありませんか? タイ赴任でWeb担当になったものの、前任者はネット集客に手をつけておらず、まずは自分で調べ始めた、という方も少なくないと思います。さらにUI、UX、SEO、LPなどの専門用語が次々に出てくるのでどこから手を付ければよいのやらと途方に暮れることでしょう。
バンコクのWeb制作会社に依頼する際に、言葉の壁で会話がかみ合わないのは避けたいところ。この記事では、担当者と話す前に最低限知っておくべき用語をわかりやすく解説します。
とは言え、実際の打ち合わせで「最近はLLMOも配慮して制作していきますので、AI対策もご安心ください。」などという言い方をするような担当者がいたら少し気をつけたほうが良いかも知れません。一見難しそうに聞こえる言葉を並べて話をするのは、その言葉を理解している人に向けてしか話す気がないということですから。
それでは、見ていきましょう。
目次
まず知っておきたい基本編
- Webサイト Webサイトはインターネット上に公開された複数のページの集合体。World Wide Web、略してWebは、インターネット上で情報を相互に結びつけ、公開・閲覧できるようにするシステムを指します。「世界に広がる蜘蛛の巣」という意味で、複数の情報がリンクで蜘蛛の巣のように繋がっている様子がその語源です。
- ホームページ 日本語においてはWebサイトと同じ意味で使う場合があります。Webサイトのトップページをホームページと呼ぶこともあるので気をつけましょう。タイ語の場合では เว็บไซต์(Webサイト)と呼ぶので、Webサイトで呼ぶことにしておくのが良いでしょう。
- Webページ Webサイトの中のページまたは、ウェブ上にあるページを指す。
- URL インターネット上の住所と考えると分かりやすいです。WebブラウザでURLを開くと特定のページが開かれます。
下記はどれもURLを指します。
https://masatoshigoto.asia
https://masatoshigoto.asia/service/
https://masatoshigoto.asia/contact
https://[ドメイン名]/[パス]の構造でなっている。 - ドメイン ドメイン名または独自ドメインとも呼ぶ。ドメインはURLの一部で、上の例では masatoshigoto.asia の部分を指す。誰かに取得されていなければ、好きな名前のものを選ぶことができる。.asia の部分は .comや .co.th などを選ぶことができる。.asia にはアジア向け、.com にはカンパニー(会社)向け、.co.th にはCompany in Thailand(タイの会社)向けなどそれぞれに意味がある。.co.th ドメインの取得には会社の登記書(ใบหนังสือรับรอง)の提出が必要。
- ウェブブラウザ ブラウザとも呼ぶ。インターネット上のWebページやPDFファイルなどを閲覧するためのアプリケーション。Chrome、Safari、edgeなどがある。スマホのSafariなどもブラウザで、「スマホのブラウザで確認します」と言ったりもする。
- SSL 略まで覚える必要はないが、Secure Sockets Layerの略で、ウェブブラウザとサーバーの間で通信データを暗号化し、改ざんやなりすましなど不正利用を防ぐための方法。導入したサイトではURLが「https://」で始まり、ブラウザに鍵マークが表示される。以前はSSL対応していないWebサイトをたまに見ることがあったが、2014年にGoogleが評価にSSLを入れたこともあり、今ではほとんど見なくなった。
- サーバー Webサイトの画像や動画なども含めたファイルを置いておく場所。利用者がブラウザからドメインにアクセスするとサーバーから利用者のコンピューターにデータが送られて閲覧ができる。1台のサーバーを複数のユーザーで使う共用サーバー、1台のサーバーを分けて専用環境として利用できるVPSサーバー、1台のサーバーをまるごと自分だけで利用できる専用サーバー、複数のサーバーをネットワークでつないで利用するクラウドサーバーなど複数のタイプがあり、料金や管理のしやすさ、性能や自由度が異なる。
- コーポレートサイト 企業の公式サイトのこと。会社概要、代表挨拶、沿革、事業内容、サービス紹介などを掲載し、企業の信頼性やブランドイメージを伝える役割を持つ。商談や採用につながる可能性をつくることができるし、AIもWeb上にある情報を元に吐き出すので、適切なコーポレートサイトを持っておくのは企業にとってとても有用。
- ECサイト いわゆる通販サイトのこと。E-Commerceの略で、Webサイト上で商品やサービスを掲載し、利用者がオンラインで購入・決済できる。
- LP ランディングページの略。LPページとも言う。比較的多く使われるので聞いたことのある方もいるかもしれません。普通のWebサイトではいろいろな情報を載せているのに対し、LPは「ひとつの目的」にしぼって作られます。たとえばあるサービスを良く知ってもらい問い合わせに繋げたいような場合に有効です。
また、「Landing = 着地する」に習って、検索や広告から流入したユーザーが最初に“着地”するなページのことを呼ぶ場合があります。どこのページからサイトの閲覧が始まったかを確認する際に使ったりします。
- レスポンシブデザイン Webサイトを閲覧する端末や画面サイズに応じて、レイアウトや表示を自動的に調整する構築手法。1つのHTMLファイルとCSSで、PC・タブレット・スマホなどさまざまなデバイスに最適化して表示できる。レスポンシブデザインができたことにより、PC用とスマホ用で別々のページを制作する必要がなくなった。
- 移行 Webサイトのサーバーを引っ越しする時に使う言葉。「新しいサーバーにWordPressのデータを移行をする」のように使う。
- 移管 ドメインの管理会社や所有権を移す時に使う言葉。「Aのドメイン管理会社で取得したドメインだが、担当者が変わるのでBのドメイン会社に移管する」のように使う。ドメインの移管くらいでしか使ったことがないかも知れない。
- Google広告 リスティング広告とも呼ぶ。Googleが提供するインターネット広告サービス。自社の検索結果が低くても、Google広告を利用することで検索結果の上位に表示させることができる。少額から始められるため、素早く集客をしたい場合に有効。
これが分かれば怖くない中級編
- SEO 略語が多いので一応書いておくと、Search Engine Optimizeの略。検索エンジンに対して最適化しましょう、ということ。Googleなどの検索結果で上位に出るように工夫することです。ページのタイトルをわかりやすくする、文章を整理する、サイトを速くするなどの積み重ねで評価が上がります。いくら良いサービスでも見つけてもらえなければ意味がないので、Web集客の基本の「き」となります。
- LLMO Large Language Model Optimizationの略。ChatGPTのようなAIに自分の会社の情報を正しく引用してもらう工夫です。AIはWeb上の情報を学習して答えを出すので、サービス内容や会社概要をわかりやすく載せておくことが大切になります。将来的にはSEOやAEOと同じくらい重要になると考えられています。
- WordPress ワードプレス。CMSと呼ばれるものの代表格。世界中のWebサイトの4割以上が使っていると言われるます。多く使われているの分、ウイルスやマルウェアの標的にもなりやすいので、こまめなアップデートが吉。プラグインをインストールすることで、コーポレートサイトやECサイト、ブログによる情報発信など様々なタイプのWebサイトを作ることができます。
- CMS コンテンツマネジメントシステムの略。要するに専門知識がなくてもWebサイトを作ったり更新できる仕組み。「誰でも簡単に」と言われますが、実際にやってみると思い通りにいかないことも多いようで、弊社でも自分でやってみてうまくできないので、やはりプロにお願いしますというケースがたまにあります。まずは触ってみるのも良いかも知れません。
- プラグイン 機能を追加するプログラム。ワードプレスなら、問い合わせフォームを作ったり、フォームからの送信内容をGoogleスプレッドシートに保存したり、画像を軽くして表示を早くするなど、便利なことがいろいろできます。ただし入れすぎるとページが重くなるので、プラグインを使わずに実装できるものはその方が良い場合もあります。
- パーマリンク 1つの記事ページにつけられるURLのこと。自社でブログを更新する場合には覚えておくのが良いでしょう。その記事が想起できるような短い語句でURLを作ります。例えばこのページであれば/web-terms-basics のように「Webの基本的な用語」としています。
- アクセス解析 Webサイトに「どれくらい人が来ているか」「どんなページをよく見られているか」などを調べること。Googleが提供するツール「Google Analytics(GA4)」を使います。弊社では毎月のレポートもしています。
- コンバージョン CVとも記す。Webサイトで達成したいゴールのことです。問い合わせ、資料ダウンロードなど成果となる行動を指します。
- KPI こういう略語が多いのですが、Key Performance Indicatorの略。コンバージョンまでの目標数値のこと。例えばバンコクのWeb制作会社で「月の問い合わせ5件」がコンバージョンであれば、月1,000アクセスを集める(1,000アクセスの根拠は、CV件数 = アクセス数 x コンバージョン率)や、「バンコク Web制作会社」のキーワード検索で 3位以内に表示されるなどになる。そして、これらを実現するためには何をする、というように考えていきます。
- KGI KPIとセットで使われることが多い指標で、Key Goal Indicatorの略。最終的なゴールを表す数値目標のことです。例えばバンコクのWeb制作会社であれば「年間売上500万バーツの達成」や「新規顧客5社の獲得」といった最終目的がKGIになります。KPIがその達成のための中間指標(問い合わせ件数やアクセス数など)だとすると、KGIは最終的にビジネスとしてどこを目指すかを示す指標です。
- UI User Interfaceの略。「ユーザー = 利用者」が画面上で実際に触れる部分のことです。メニューの位置やボタンの大きさ、文字や色、「利用者が使うのはきっとソファに横になりながらスマホで閲覧だから〜」というようなことも含めて考えます。
- UX User Experienceの略。サイトを使ったときに得られる利用者の体験のこと。「目的の情報まで迷わずにたどり着けた」や「書かれている文章を読んで心打たれた」などは良いUXで、「ページの読み込みに時間がかかったので他のサイトを見に行った」や「文字が小さくて読みづらくて拡大・縮小を繰り返すことになった」などは悪いUXです。
- ウイルス コンピューターに感染して悪さをするプログラムのこと。人間の体に風邪やインフルエンザのウイルスが入るのと同じイメージです。感染するとサイトが改ざんされたり、情報が盗まれたりする危険があります。
- マルウェア 「悪意のあるソフトウェア」をまとめて呼ぶ言葉です。ウイルスもマルウェアの一種です。弊社でも過去に2件、マルウェアにやられたと問い合わせをいただき対応をしたことがあります。膨大にあるワードプレスファイルの中に悪さをするファイルを仕込まれていて、それを見つけ出して駆除する作業でした。自分は大丈夫と考えるのが常ですが、備えあれば憂いなし。保守管理をしっかりと行いましょう。
- HTML これももちろん略は覚える必要などないが、Hyper Text Markup Lanuageの略。Webページの骨格をつくるための言語。見出し、文章、画像、リンクなど、ページに「何を」「どの順番で」表示するかを記述する。HTMLの記述の仕方もGoogleの検索結果の基準のひとつとなっているので特に気を使う必要がある。
- CSS Cascading Style Sheetsの略。HTMLで作った骨格に見た目のデザインをつけるための言語。文字の色や大きさ、背景、レイアウト、余白などを指定し、見やすく整える。簡単なアニメーションも行える。
あなたもWeb業界に上級編
- JavaScript Webサイトに動きつけるためのプログラミング言語。画像のスライドや問い合わせフォームの入力チェック、スクロールに合わせて画像が表示されるなど、UXを向上させられる。
- PHP Web開発に使われるプログラミング言語。ページを開くたびに「データベースから記事を取り出して表示する」など、動的なページを作る仕組みに使われます。Wordpressで使われているプログラミング言語。
- API Application Programinig Interfaceの略。異なるシステム同士をつなぐための「受け渡し口」のようなものです。例えば「GoogleマップをWebサイトに埋め込む」や「インスタの投稿をWebサイトに表示させる」などにAPIが使われます。
- 内部リンク サイト内のページ同士をつなぐリンクのこと。たとえばブログ記事からサービスページに誘導するなど。利用者にとって関連情報を辿れるるので、分かりやすい構造となる。Googleの評価にも良い影響を与える。
- 外部リンク 他のサイトへのリンク、または他のサイトからのリンクのこと。特に信頼性の高い外部サイトからリンクされると、Googleからの評価が高まりやすい。
- モバイルフレンドリー スマホでも見やすく、使いやすいサイトであること。文字が小さすぎない、ボタンが押しやすい、横スクロールしなくてもいい、待ち時間が少ない、使い方が一般的であるなどがポイント。Googleも評価基準にしています。
- クエリ 検索エンジンに入力するキーワードのこと。たとえば「バンコク Web制作会社」と検索したら、その検索語句がクエリです。Search Consoleで確認できる代表的な指標のひとつです。
- Search Console Googleが提供しているWebサイト運用のサポートツール。自分のサイトが「どんなキーワードで検索されているか」「検索結果に何回表示されたか」「クリックされたか」などを確認できる。検索エンジンに認識されていないページを調べることもできるなど、SEOの基本チェックに欠かせません。
- コード Code。プログラムの文字のこと。HTMLやCSSなども「コード」と呼ばれます。見た目はただの英数字の並びですが、ブラウザを通すと画像が表示されたり、レイアウトが整って表示されます。
- コーダー コードを書く人のこと。
- フロントエンドエンジニア ユーザーが実際に見る側をつくる人のこと。後に出てくるバックエンドと分けてこう呼ぶ。
- バックエンドエンジニア ユーザーからは見えない裏側の部分を作る人のこと。いわゆるシステムの設計や開発を行う。
- マークアップエンジニア HTMLやCSSを使ってコードを組む人のこと。コーダーと同じだし、フロントエンドエンジニアとも同じ。業界が成熟してくるとともに業務が細分化されて様々な呼び名が生まれ、WebデザイナーやWebエンジニアなどもある。業界内的には意味があるが、外部的には話がややこしくなるので私はWeb制作をすべてやる人ということでWebデザイナーで統一している。
まとめ
Webサイト制作や運用における基本用語を並べてみましたが、何も分からなくても全く問題ない、という考え方もあると思います。分からないことは、知っている人にお願いするというやり方です。何も分からなくても問題ありません。お話を伺ってから、Webサイトをつくることによって御社にどのような良いことが起こりうるのかから分かりやすく説明いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。